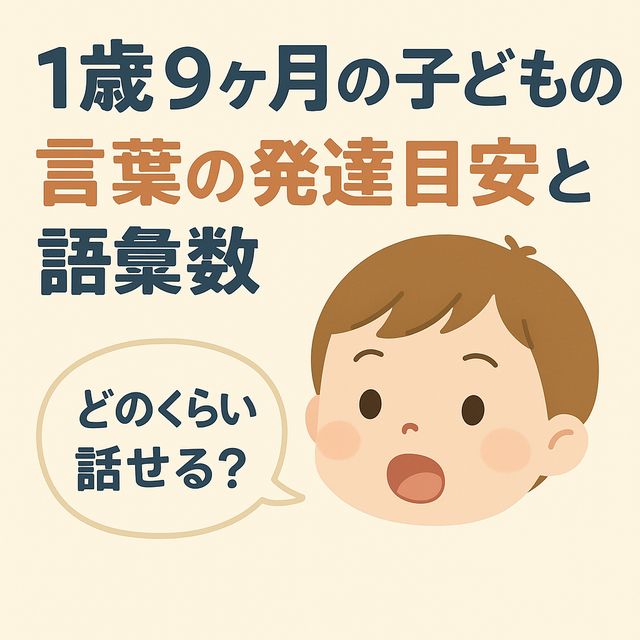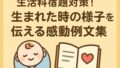「1歳9ヶ月の子ども、言葉ってどのくらい話せるのが普通?」
そんな疑問を抱いているママ・パパも多いのではないでしょうか。
この時期は、言葉の発達に大きな個人差が現れる時期でもあり、わが子の様子に不安を感じることもあるかもしれません。
この記事では、「1歳9ヶ月 言葉どのくらい」というキーワードに基づき、平均的な語彙数や発達目安、親の関わり方、発達が気になる場合の対応方法まで、具体的かつ分かりやすく解説します。
「言葉が遅い?」と焦る前に、正しい知識と視点を持って子どもと向き合いましょう。
1歳9ヶ月の言葉の発達目安とは?
言葉の理解と表出の違い
1歳9ヶ月の子どもにおける「言葉の発達」は、「理解している言葉」と「実際に話す言葉」に分けて考える必要があります。
多くの保護者は「話せる言葉の数」ばかりに注目しがちですが、実はこの時期の子どもは、話せる言葉以上に多くの語を理解しています。
たとえば、「ママ、抱っこして」「おもちゃ取って」といった指示に的確に反応できるようであれば、言葉の理解力が順調に育っているといえるでしょう。
言語理解は、言語表現(話すこと)よりも早く発達するため、発話が少ないからといってすぐに心配する必要はありません。
特に慎重な性格の子どもは、じっくりと観察してから話し出す傾向があります。
一般的な語彙数の目安
1歳9ヶ月の子どもが話せる語彙数の平均は、おおよそ30〜100語程度とされています。
ですが、これはあくまでも目安であり、20語前後しか話さない子もいれば、200語近く話す子もいます。
言葉の発達は非常に個人差が大きいため、数だけで一喜一憂する必要はありません。
保育士や言語聴覚士の間でも、「この時期は『二語文』が出始めるかどうかが一つの目安」とされています。
たとえば、「ママ、きて」「ワンワン、いた」など、二つの言葉を組み合わせて意味のある表現をすることができるようになっていれば、言葉の発達は順調といえるでしょう。
個人差が大きい理由
1歳9ヶ月という年齢は、心身ともに発達が著しい時期である一方、成長のペースは子どもによって大きく異なります。
家庭での言語環境や、兄弟姉妹の有無、保育園に通っているかどうかなど、日々の生活環境が発達に影響を与えるため、言葉の発達にも幅があるのです。
たとえば、兄や姉がいる子どもは周囲の言葉をたくさん聞いて刺激を受けやすく、話し始めが早い傾向があります。
一方で、一人っ子で親が子どもの気持ちを先回りしてくれる環境では、子どもが自分から言葉で伝える機会が少なくなり、発話がゆっくりになることもあります。
このように、言葉の発達は「年齢=語彙数」と単純には測れません。
周囲との比較ではなく、わが子の様子をしっかり観察しながら成長を見守ることが大切です。
1歳9ヶ月で見られる具体的な言語表現
一語文から二語文への移行
1歳9ヶ月頃の子どもは、発語の種類として「一語文」から「二語文」への移行が見られる時期です。
一語文とは、「ワンワン」「ママ」「ブーブー」など、単語単体で気持ちや要求を表す言葉。
一方、二語文とは、「ママ、だっこ」「ブーブー、ない」など、2つの単語を組み合わせて意味を持つ簡単な文章のことです。
この時期にすでに二語文が出ている場合は、言語発達が比較的早い傾向にあります。
ただし、まだ一語文が中心の子どもも多くいます。
ポイントは、「言いたいことを伝えようとしている姿勢があるか」という点です。
たとえば、指さしをしながら「ワンワン!」と発するのも、立派なコミュニケーションです。
日常生活でよく使う言葉の例
子どもが最初に話す言葉は、身近な人や物、日常的な行動に関するものが多いです。
たとえば、「ママ」「パパ」「ワンワン」「ブーブー」「まんま(ごはん)」「バイバイ」「ねんね」「あっち」などがよく使われます。
中には、「いたい」「ない」「ちょうだい」といった感情や要求を表す言葉も出てくるようになります。
言葉の使い方には個性があり、特定の語を何度も繰り返して使う子もいれば、語彙を広く使い分ける子もいます。
重要なのは、子どもが言葉を「使って伝える」経験を積んでいるかどうかです。
発音の特徴と親の理解のコツ
この年齢の子どもは、まだ舌や唇の運動が未熟なため、正しい発音が難しいこともあります。
「さかな」が「たなた」になる、「くつ」が「ちゅちゅ」になるといった具合です。
大人から見ると何を言っているか分からないことも多いですが、子どもの表情やジェスチャー、指さしなどを総合的に見て、何を伝えたいのかをくみ取ってあげることが大切です。
親が「それはこういう意味だね」と共感しながら言い直してあげることで、正しい言葉を自然と学んでいくことができます。
たとえば、子どもが「ちゅちゅ」と言ったときに、「ああ、くつを履きたいんだね。くつ履こうね!」と返すような対応が、言語の発達を後押しします。
言葉の発達を促す親の関わり方
日常的な声かけの重要性
1歳9ヶ月の子どもの言語発達を促すには、親の「日常的な声かけ」が最も効果的です。
この時期の子どもは、親の言葉や語りかけからたくさんの語彙を吸収しています。
たとえば、「おむつ替えるよ」「靴を履こうね」「お水飲む?」など、日常の行動に合わせて言葉を添えることで、自然と言葉を覚える環境が整います。
また、子どもが発した言葉に対してしっかり反応することも大切です。
「ブーブー」と言ったら「そうだね、ブーブーが走ってるね!」と返すことで、子どもは「言葉を使うと伝わるんだ」と実感し、発語の意欲が高まります。
絵本の読み聞かせの効果
絵本の読み聞かせは、言語発達を促進するうえで非常に効果的な手法です。
文章のリズムや言葉の繰り返し、豊かな語彙表現が子どもの耳に届くことで、自然と語彙力が増していきます。
ポイントは「一方的に読む」のではなく、やり取りをしながら読むこと。
「これは何かな?」「ワンワンがいるね」など、絵を指さして質問をしたり、答えを待ったりすることで、子どもとの対話が生まれ、言葉のキャッチボールができます。
読み聞かせは1日5分でも構いません。毎日のルーティンに取り入れて継続することが大切です。
子どもの発話を引き出す遊び方
遊びの中にも、言葉の発達をサポートするヒントがたくさんあります。
たとえば、積み木遊びやおままごと、ぬいぐるみでのごっこ遊びでは、「これなあに?」「どうするの?」などの質問を投げかけることで、子どもが言葉を使う機会を自然に増やすことができます。
また、「○○ちゃん、できたね!すごいね!」と声をかけてあげることで、子どもは自信を持ち、さらに話したいという気持ちが高まります。
言葉が出にくいと感じるときは、無理に言わせようとせず、「まずは楽しい!」という気持ちを優先した遊びを通じて関わるようにしましょう。
言葉の発達が遅いと感じたときの対応
専門家に相談すべきタイミング
1歳9ヶ月で言葉があまり出ていない場合、すぐに心配する必要はありませんが、いくつかのサインに注意することは大切です。
たとえば、
- 視線が合わない
- 指さしをほとんどしない
- 簡単な指示に反応しない(「ちょうだい」「おいで」など)
- 発語がまったくない
こうした状況が複数見られる場合は、言語だけでなく全体的な発達の確認が必要かもしれません。
心配な点がある場合は、自治体の乳幼児健診(1歳半健診など)で相談したり、小児科医、言語聴覚士、児童発達支援センターなどの専門機関に問い合わせてみましょう。
早期にアプローチを行えば、よりよいサポートを受けられる可能性が高まります。
家庭でできるサポート方法
言葉の発達が気になるときこそ、家庭での「安心できるやりとり」が重要です。
親が焦って「これ何?言ってみて」などと急かしてしまうと、逆に子どもがプレッシャーを感じて話すことを避ける場合もあります。
代わりに、「○○したいんだね」「これはバナナだよ、美味しいね」といったように、子どもの行動や感情に寄り添った言葉をかけることで、自然に言葉のモデルを見せることができます。
また、音楽や童謡を一緒に歌う、手遊びを楽しむといった方法も、言葉のリズムや発音を覚えるうえで非常に効果的です。
他の発達指標との関連性の確認
言葉だけでなく、他の発達指標とのバランスを見ることも大切です。
たとえば、「歩くのが早かったから言葉はゆっくり」「人見知りが強いから話すタイミングを見ている」といった子どももいます。
発語が少なくても、身振りやアイコンタクトで意志を伝えているようであれば、総合的に見て順調に発達している可能性が高いです。
発達には「得意・不得意のタイミング」があることを理解し、焦らず見守る姿勢が求められます。
どうしても気になる場合は、発達全体を確認してくれる小児科や専門機関での相談をおすすめします。
言葉の発達に関するよくある質問と回答
男の子と女の子で発達に差はあるのか?
はい、一般的に言葉の発達については「女の子の方が早い傾向がある」といわれています。
これは統計的にも見られる傾向で、発語数や二語文の使用開始時期にやや差が出ることがあります。
しかし、あくまでも「傾向」であり、個人差が大きいため、男の子だからといって遅れていてもすぐに問題視する必要はありません。
重要なのは、子どもが「伝えたい」「わかってもらいたい」という気持ちを持ち、それを行動や発語で表現しようとしているかどうか。
性別よりも、その子自身の様子をしっかり見守ることが大切です。
バイリンガル環境が言葉の発達に与える影響
両親が異なる言語を話していたり、家庭内で2つの言語が飛び交うバイリンガル環境では、一時的に発語がゆっくりになることがあります。
これは、複数の言語情報を同時に処理するための時間が必要だからです。
ただし、バイリンガル育児が言葉の発達に悪影響を及ぼすことは基本的にありません。
むしろ長期的には語彙力や言語処理能力にプラスに働くことも多く、安心して大丈夫です。
ポイントは、1つの言語でもしっかりとしたモデル(文法や語彙)を子どもに示すことです。
たとえば「パパは英語、ママは日本語」といった役割分担を明確にすることで、子どもが混乱せずに吸収しやすくなります。
兄弟姉妹の影響と対応策
兄弟姉妹がいる場合、言葉の発達にプラスにもマイナスにも影響する可能性があります。
上の子がたくさん話す環境では、下の子は自然と語彙を学びやすい反面、兄や姉が何でも代弁してしまうと、自分で話す機会が減り、発語が遅れることも。
この場合、下の子にも「○○ちゃんはどう思う?」「これ何て言うんだっけ?」といったように、発話の機会を意識的に作ることが大切です。
また、兄弟と遊んでいるときの会話をさりげなく観察することで、家庭では見られない成長が感じられることもあります。
家庭内でのやりとりが自然な形で豊かになれば、それがそのまま言葉の発達につながります。
兄弟姉妹の存在を上手に活かして、楽しく学べる環境を整えてあげましょう。
まとめ
1歳9ヶ月の子どもの言葉の発達には大きな個人差があります。
平均的な語彙数は30〜100語程度とされますが、それより少なくても「理解力がある」「身振りで意思疎通ができている」などのポイントが見られれば、順調に育っている可能性が高いです。
この時期に大切なのは、親子のあたたかいやりとり。毎日の声かけや絵本の読み聞かせ、遊びを通じた関わりが、子どもの「話したい!」を引き出します。
言葉が出にくいと感じても、焦らず見守りつつ、必要に応じて専門家のサポートを受けることも選択肢です。
子どもは一人ひとり、自分のペースでしっかり成長しています。
言葉の数にとらわれすぎず、日々の小さな変化を大切にしながら、一緒に成長を楽しんでいきましょう。